2025年の診療報酬改定を踏まえ、心臓ペースメーカーや植込型除細動器などの遠隔モニタリング加算について関心が高まっています。本記事では、診療報酬点数や算定要件、診療報酬区分と枝番など、実務に必要なポイントを簡潔にまとめました。
✅ 遠隔モニタリング加算とは?
遠隔モニタリング加算は、心臓植込み型デバイス(ペースメーカーやICDなど)を装着した患者に対して、遠隔通信機器を活用して状態をモニタリングし、必要な指導管理を行った場合に算定できる加算です。
📊 診療報酬点数(2025年時点)
| 対象機器 | 診療報酬区分 | 枝番 | 点数(月あたり) |
|---|---|---|---|
| ペースメーカー(PM)・CRT-P | B001-12 | ロ | 260点 |
| ICD・CRT-D | B001-12 | ハ | 480点 |
🏥 対象患者
-
体内植込式のペースメーカーやICDを使用している外来患者
-
入院中の患者は対象外
📝 主な算定要件
-
定期的な遠隔モニタリングの実施
臨床上必要な情報(バッテリー残量、作動履歴、不整脈発生など)を通信機器で取得・評価。 -
適切な指導の実施
得られたデータをもとに医師が必要な療養上の指導を行い、その内容を診療録に記載。 -
患者の同意と計画策定
遠隔管理を行う前に、対面診療+遠隔モニタリングを組み合わせた計画を作成し、患者の同意を取得。 -
対象期間
前回の対面受診月の翌月から、次回の対面受診月の前月までが加算対象。最大11か月分まで算定可能。
🏥 施設基準(抜粋)
-
厚生労働省の「情報通信機器を用いた診療指針」に沿った診療体制を持つ保険医療機関であること
-
緊急時には、概ね30分以内に対面診療が可能な体制を有していること
💡 実務上の注意点
-
加算は毎月の管理ではなく、前回対面診療から次回までの間に行った遠隔管理に対して算定
-
記録が不十分な場合、監査で指摘される可能性もあるため、診療録の記載は徹底が必要
-
オンライン診療料など、他の加算との併算定制限がある場合があるため、注意が必要
🔗 関連リンク
✍️ まとめ
心臓ペースメーカー等における遠隔モニタリング加算は、デジタル技術を活用した患者管理の促進に向けて重要な診療報酬制度です。2025年時点では、PM・CRT-Pで260点、ICD・CRT-Dで480点という設定となっており、適切な運用と記録が求められます。
診療報酬の正しい理解と活用は、医療機関の経営や患者ケアの質にも直結します。今後も改定情報に注目していきましょう。
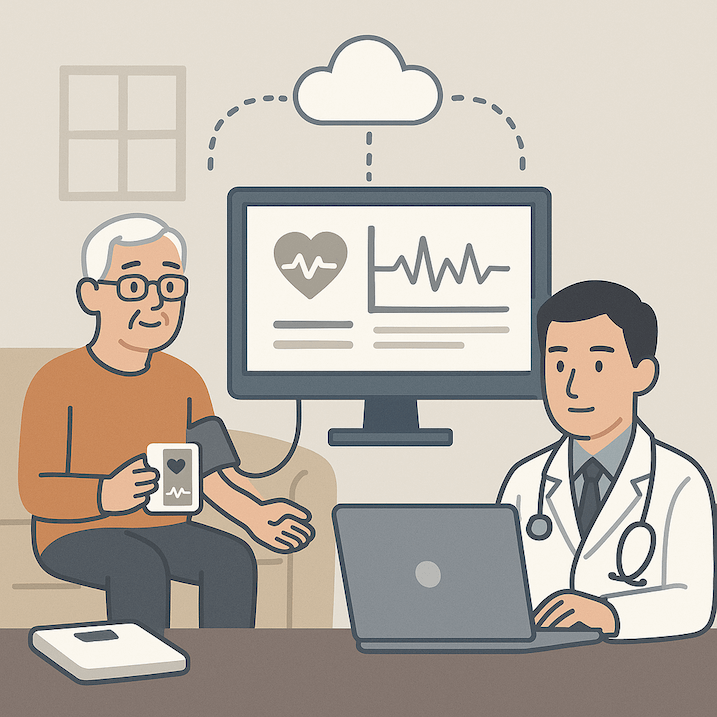
コメント